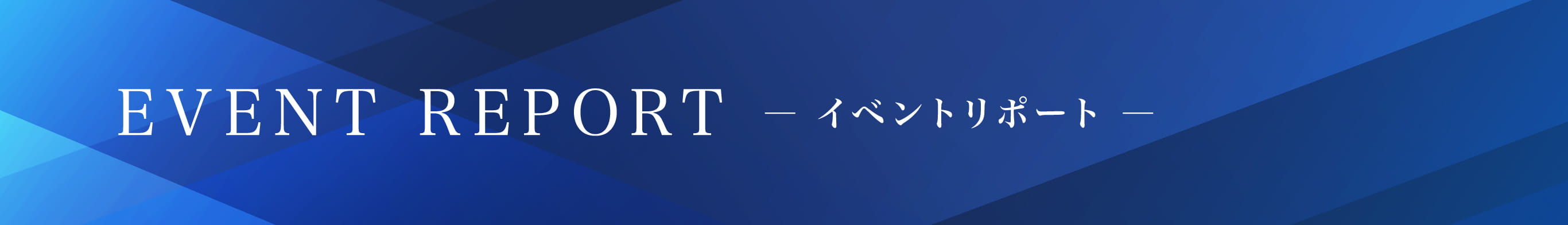新潟日報LEADERS倶楽部宮家邦彦氏講演会
新潟日報リーダーズ倶楽部は、発足から14年目。2025年度最初の事業として、7月1日に元外交官でテレビでもおなじみの宮家邦彦氏を招き講演会を開催しました。約70人の企業経営者らが耳を傾けた講演の内容を紹介します。

講演
最新の国際情勢と
日本経済に与える影響
パラダイムシフト迎える世界で
日本はいかに生き延びるか
キヤノングローバル戦略研究所 理事・特別顧問
宮家 邦彦 氏
トランプ関税から見えるアメリカ製造業の空洞化
今日は、私がどのように国際情勢を見ようとしているのかを話したい。まずは米トランプ大統領の相互関税。これは経済学者には絶対に理解できない。なぜなら、トランプ氏がやっているのは経済政策ではなく、「けんか」だから。関税を上げたらアメリカの経済が良くなるわけはない。その本質は、中国との競争に勝ち目がないかもしれないと心配したあまりのけんかなのだ。
今までは人と物と金が自由に流れる、自由貿易をしてきた。特に活発化したのが1980年以降。為替自由化により、貿易赤字国の通貨価値が下がり、貿易黒字国の通貨価値が上がるということがなくなった。逆に、安全保障上強力なアメリカにお金がどんどん行く。その結果、何が起きたか。慢性的なドル高になった。そして、アメリカの製造業の空洞化が始まった。85年のプラザ合意でドル高を修正したつもりが、40年間それは変わらなかった。その結果、アメリカの製造業は外国へ出て行ってしまった。アメリカにはサービス業があり金融業がある、だから大丈夫だというのが今までの定説だったが、私はそうではないと思う。もう物が作れなくなったアメリカが、強力な製造能力を持ち、約14億人の人口がいる中国と競争できるのだろうかと考えての最後の手段なのではないか。
「忘れられた人々」の怒り トランプ政権が受け皿に
昨年、世界各地で行われた選挙はどういう意味を持つのか。まず韓国の与党が負け、イギリスの保守党も大敗した。自民党も負け、アメリカではバイデン氏、ハリス氏が負けた。その共通点を米紙ニューヨークタイムズが分析している。「荒れ果てた工業地帯や田舎に住む、忘れられた人々が怒っている。その怒りが選挙結果に至った」と。
トランプ現象とはトランプ氏がつくったものではなく、不満の受け皿にトランプ氏がなったと捉えている。都市に住んでいないブルーカラーを中心とする、マニファクチャリング(製造業)を支えた人たちが抱く「IT長者がなんだ」「移民が来てけしからん」という気持ちを吸い上げたのがトランプ政権。この人たちの不満が消えない限り、トランプ現象は続くと私は見ている。
日本も同じ。この国には失われた30年がある。私の息子の給料は私の初任給より少ない。彼らの不満が自民党の敗北につながったけれども、日本はそれほど格差がひどくないから、その程度で収まっている。もしトランプ氏のような政治的天才がこの国に現れて国民の不安をすくい上げることができたら、日本の政治は変わってしまう。それでいいのかというのが私の問題意識だ。
「地政学リスク」の解釈と戦いから学ぶべきこと
いろいろな経済誌によく出てくる言葉「地政学リスク」。それはある国もしくは民族の歴史的脅威はどこから来るかということ。そして山・川・海・島といった地理を念頭に置いて、政治的・軍事的にどう対応したかを学べば、将来似たような脅威が出てきた時の参考になるかもしれない、ということだ。
例えばロシアの場合、西、南、東の3方向から脅威を受け続け、攻め入られる前に緩衝地帯を拡大することで対抗してきた。そして東欧諸国とワルシャワ条約機構を結成し、北大西洋条約機構(NATO)に対抗する。しかしソ連が崩壊すると、みんなNATOにくら替え。さらにウクライナがNATO加盟の動きを見せたことで、ウクライナへ侵攻したのだ。
われわれがウクライナ戦争から学べることは五つ。軍事力がなければ国は守れない。情報戦に勝たなければならない。同盟がないと国は守れない。自ら血を流さない国を同盟国は守らない。そして最も重要なことは「専門家は当てにならない」。なぜか。人間は間違えるからだ。独裁者が判断を間違えば戦争が起こる。
国際情勢は「流れ」で読む 歴史的な視点から予測を
国際情勢を読み解き、戦略を考えるのに重要な視点は歴史。歴史は長編動画で、新聞の1面に出ている写真は長編動画の1コマに過ぎない。ストーリーを把握しておかないと、切り抜いた静止画が何を意味するか分からない。細かいことは捨てて、歴史から将来を予測する訓練をしなければならない。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。歴史は繰り返さないが時に韻を踏む。そして、有事には政治家は判断基準を変える。この三つが私の歴史に関する教訓だ。
昨年トランプ氏が勝ったときに、第2次世界大戦後から続く自由な国際主義は一度足踏みをする時期に来ているのではないかと感じた。80年間の幸せな戦間期は終わるかもしれない。世界はパラダイムシフトを迎えつつある。その中で、日本が再び国際的な信頼を取り戻したいのであれば、歴史から学び、将来を予測した上でやるべき事をやれる国であることを示していかなければならない。今こそがチャンスだと私は思う。


プロフィール
キヤノングローバル戦略研究所 理事・特別顧問
宮家 邦彦(みやけ くにひこ)氏
1953年神奈川県生まれ。1978年外務省入省。日米安保条約課長、在中国大使館公使、在イラク大使館公使、中近東アフリカ局参事官などを経て2005年に退官。外交政策研究所代表、立命館大学客員教授、キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問。主な著書に『通説・俗説に騙されるな! 世界情勢地図を読む』『グローバルサウスの地政学』など多数。